




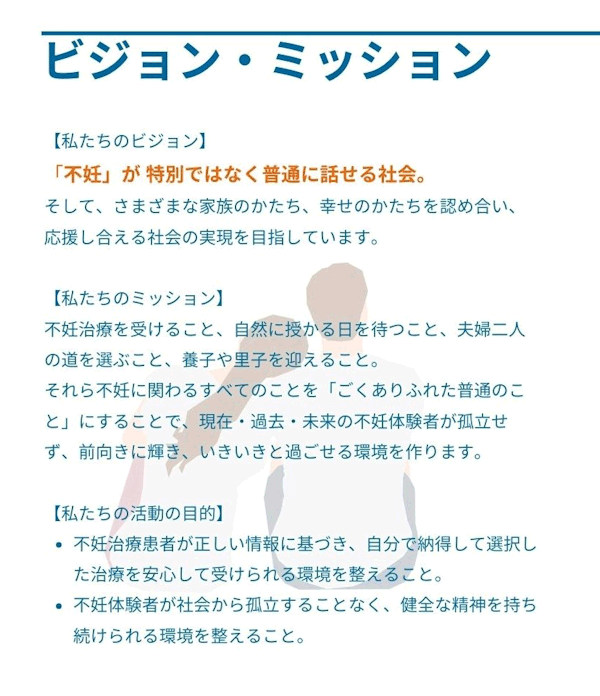

「当事者が当事者の心のケアをする」重要性に着目し、不妊ピア・カウンセラーを自ら養成して、カウンセリング事業を行なっています。
不妊ピア・カウンセラーは、不妊という同じ体験をしたからこそ、その悩みやつらさ、当事者が置かれている状況を理解できることが多く、
不妊で苦しむ人にとっては貴重な支援者となっています。




| 精神的サポート | 不妊ピア・カウンセラー養成講座では、当事者が当事者の心のケアをする重要性に着目し、不妊ピア・カウンセラーを自ら養成しています。 |
| 不妊ピア・カウンセラーおよび臨床心理士による面接カウンセリング、電話相談、グループカウンセリングで、不妊にまつわるさまざまな気持ちに寄り添っています。 | |
| 仲間づくり | ひとりぼっちと感じてしまいがちな不妊当事者に向けて、おしゃべり会や懇親会を開催。当事者同士の交流の場を提供します。 【参加者の感想より】
|
![]()
不妊当事者・不妊治療の現状を、当事者以外の方に広く知っていただけるよう活動しています。
これまでに薬剤の認可に関して提出した要望書は多数承認され、当事者の時間的負担と金銭的負担を軽減できました。
2016年には厚生労働大臣と一億総活躍担当大臣へ「仕事と治療の両立に関する要望書」を提出し、内閣府から出された政府方針に組み込まれました。




| 署名活動 | 2007年より不妊患者の経済的負担軽減等のための署名活動を行なっています。 |
| アドボカシー | 厚生労働省などに9つの要望書を提出し、6つ(新薬許可、自己注射など)が実現しました。また、国会での勉強会を開催させていただいたり、不妊に関わる勉強会に参加させていただき、意見交換をさせていただいています。 |
![]()
さまざまな年代・立場の人を対象に、不妊治療の正しい知識と理解を普及させる活動を行なっています。
企業向け、自治体向け、学生向けと、それぞれのニーズにあった内容でプログラムを準備し、当事者の具体的な悩みや負担を当事者自らが語る不妊セミナー、
当事者の体験談発表会、妊娠・出産とキャリアを考える勉強会の企画などを行なっています。特に企業向けでは、職場におけるコミュニケーションの改善や
ハラスメント対策に役立ててもらっています。


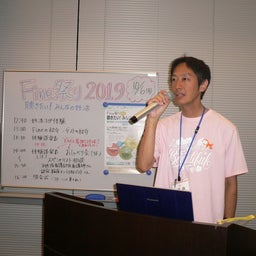

| 講演、体験談発表 | 自治体、学会、クリニックなどで講演、講義、体験談発表を行なっています。 【参加者の感想より】
|
| アンケート調査 | 不妊当事者の実態や意識・意見を収集するアンケート調査を実施しています。 2018年実施の「仕事と不妊治療の両立に関するアンケートPart?U」の結果をもとに当事者の生の声を集計・分類し、不妊白書2018を発行しました。 |
| 妊活プロジェクト | 「不妊予防」および「妊娠に関わる身体や心のケア」を一元化した事業「Fine妊活プロジェクト」を推進。企業の管理職や従業員向けに妊活や不妊に関することを正しく知ってもらうための啓発セミナーを実施しています。 |
| 情報発信 | Webサイト、メールマガジン、ブログ、プレスリリースなどによる情報発信を積極的に行ない、多数のメディアからの取材にも対応。コミュニティ放送局「渋谷のラジオ」で月1回、番組を担当し、幅広い層に啓発をしています。 |