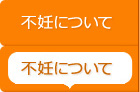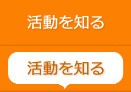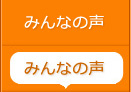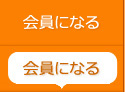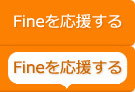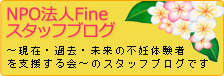- トップ >
- 活動を知る >
- 主催イベント(予告・報告) >
- 主催イベント活動レポート >
- 多様な絆のかたちプロジェクト
多様な絆のかたちプロジェクト第三弾 「里親・養子縁組養親とのオンライン交流会」
「里親、養親の方の生の声を聞ける貴重な時間でした。同じ思いを抱えている人がここにいるのだと実感できたことが何より心強かったです」
(参加者の感想)
里親と養親をされているお二人をゲストにお招きし、体験談をお聞きした後、お二人を囲んでの交流会を行ないました。

(当日撮影:ゲストのお二人と運営スタッフ)
開催日:2025年6月14日(土)10時00分-12時00分
開催場所:Zoomによるオンライン開催
参加費:無料
担当者の感想
第一弾の上映会、第二弾の講演会に続き、今回は里親と養親をされているお二人をゲストにお招きし体験談発表と交流会をオンラインで開催しました。
前半の体験談発表はどなたでも視聴可能で、後半のゲストとの交流会は「不妊・不育の経験者で実子以外の選択に関心がある方」を参加対象としました。前半と後半で対象者を分けたのは、里親や特別養子縁組について広く知ってもらいたいとの想いと、今まさに里親や養親を検討している方たちには安心して悩みを話し合える場を提供したいとの両方の想いからです。
体験談発表には2組のご夫婦を含め合わせて28名が視聴し、そのうち7名が後半の交流会にも参加しました。
体験談発表で最初にお話しくださったのは、里親をされている青山様です。43歳で不妊治療を終え、特別養子縁組を目指すも、年齢のことであきらめたそうです。しかし、親になりたいと強く願う夫のため、また自身も後悔しないために、48歳の時に里親になることを決め、2歳の男の子を迎えられました。最初は里親子であることを周囲に話さずにいたところ、これはとてもしんどく、子どもに確認せず親が決めてしまったことを反省していると話してくださいました。また、実親などとの別離体験ゆえの里子の試し行動が現れた際は、青山様が全力で拒絶をされたそうです。試し行動がひどい場合、里親も子どもを拒絶するケースもあり、負のループになる可能性があるとのお話がとても印象に残りました。里親の苦労は里親でないとわからない、だからこそ仲間とつながることがとても重要であること、また里親として学び続けることの大切さについて熱を込めて説明してくださいました。
続いてお話しいただいたのは、4年前に特別養子縁組で生後間もない女児を迎え入れたタカ様です。タカ様は、30代後半から40代半ばまで不妊治療を続けました。夫が養子で育ったため、夫から養子縁組はどうかと何度か聞かれたけれど、治療と養子縁組を同時に考えることはできなかったそうです。しかし、ある時、自分は産みたいというより親になりたいと気づき、スパッと気持ちを切り替えて里親と養子縁組の情報収集を始めることにしました。特別養子縁組をしたいと決めてからは、夫と一緒にあっせん団体を一つ一つ調べて良いと思う団体を見つけ、半年後には子どもを迎え入れました。ご自分の体験をもとに、あっせん団体を選ぶときに参考となる公のデータや養子縁組に必要な手続きなどを、詳しく丁寧に教えてくださいました。そして、申込書類や家庭裁判所の書類などの作成は自分の過去を振り返ることが必要になり大変な作業ですが、この作業が大事であること、また夫婦でたくさん話し合ってお互いに納得して足並みをそろえて進むことが大切であるとお話ししてくださいました。「家族のベースは人と人のつながりであり、どのような時間を一緒に紡いでいくか、どのように信頼関係を築いていくのかが大事」との言葉が心に残りました。
続いての質疑応答では、参加者から事前にいただいていた「家族や周囲の人に対してはどのように説明したか?」「決断の後押しとなったことは?」などの質問に答えていただきました。「実子でないことの悩みごとは?」に対し青山様が、不特定多数の人が見る学校での集合写真に子どもが写ることができなかったことや、予防接種は実親の許可が必要なケースがあること等を教えてくださいました。タカ様は、母の集まりで、母乳の話など、産むことに関わる話題の対応に困ったことを教えてくださいました。
休憩をはさんで、後半の交流会には、不妊・不育の当事者で里親や養親に関心のある7人が引き続き参加しました。二つのグループに分かれ、それぞれに青山様とタカ様に入っていただき、不妊ピア・カウンセラーがファシリテーターを務めました。途中でお二人が交代することで、参加者全員がお二人とお話しできるようにしました。両方のグループで話題になったのは、障害のある子どもを受け入れる可能性についてです。夫婦が障害のあるお子さんを育てることに不安を持っている場合、その気持ちはどこまで尊重されるのかを心配している方が多いようでした。また「子どもが希望した場合、実親に会わせることはあるのか?」「里子養育手当の使途の記録は大変ですか?」など具体的な質問もあり、お二人が、その一つ一つに誠実に答えてくださっていました。
今回の交流会が開催できたのは、アクロスジャパンの小川様、グローハッピ―の齋藤様が快くご協力してくださり、青山様、タカ様、お二人をご紹介してくださったお陰です。心より感謝申し上げます。
また、貴重なお時間を割いて参加してくださった方々、本当にありがとうございました。
(担当/Fineスタッフ 金澤佳美)

今回の内容についてご意見、ご感想(抜粋)
- 里親・養親さんとの交流会は今まであまりなかったので、貴重なお話を聞けて良かったです。不妊治療を経験された方だったので、共感しやすく、現在治療中の当事者にも寄り添って話してもらえている感じがして良かったです。
- 里親、養親の方の生の声を聞ける貴重な時間でした。同じ思いを抱えている人がここにいるのだと実感できたことが何より心強かったです。
- 普段は聞くことのできない具体的な情報収集方法やあっせん団体を選ぶ方法などが大変勉強になりました。
- 具体的な生活のご様子をお聞きできて初めて知ることも多かったです。
- 聞きにくいことも聞けて、とてもいい体験になりました。
- 内容がコンパクトにまとまっていて、あっという間でした。参加しやすかったです。ゲストとの交流は緊張したけれど、聞きたいことが聞けてイメージがしやすくなりました。
- やはり実際に体験なさっている方のお話を実際にお聞きするのは響くものがありました。
次回はどのようなものを望みますか (抜粋)
- 児童相談所に里親登録をされて養親になった方のお話もお聞きしたいです。(手続きの流れや必要なことも含めて)
- 里子さんたち(高校生以上かな)の率直な気持ちを聞きたいです。また子ども側が考える、制度や家庭内での改善案などアイデアをシェアしてもらえたらうれしいです。
- 現在まだ治療中で揺れ動いている方や、さまざまな不安を感じている方との雑談がメインの、おしゃべり会のような交流会もあったらいいな、と思います。